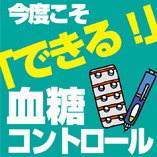 第15回 こんなときどうする? 患者さんに食べ過ぎている自覚がない!
第15回 こんなときどうする? 患者さんに食べ過ぎている自覚がない!
- 公開日: 2015/9/14
客観的に見ることのできない食習慣は、記録することで患者さんの認識を新たにすることができます。
内容や量など、細かく記載してもらい、一緒に見直してみましょう。
▼糖尿病、血糖コントロールの記事をまとめて読むならコチラ
【糖尿病】血糖コントロールの指標と方法
ケース11 患者さんに食べ過ぎている自覚がない!
食べ過ぎている自覚がないときはこうする!
まず患者さんがこれまでどのような食生活をしてきたかを知る必要があります。1日何回、何時頃に、誰と、どのような内容の食事をしているのかを、できるだけ具体的に話してもらいます。わかる範囲で構わないので、前もって1週間の食事記録をつけておいてもらうことも有効です。ただし記録があっても、必ず聞き取りは行うようにしてください。
客観的に食生活を見直すことで、「そんなに食べているつもりはない」といっていた患者さんも、実はかなりの量を食べていた事実に驚くこともあります。
また、患者さんには、「朝食は食べず、昼と夜にたくさん食べる」「コンビニのお弁当をよく利用する」「外食が多い」など問題点はさまざまありますが、それを頭ごなしに否定せず、まずはどうしてそうなるのかという理由を探るようにします。そのヒントとなるのが、その人の生活スタイルです。
1日のタイムスケジュール、仕事内容、家族関係、友人関係など、一見関係のなさそうなことが、食生活に影響を及ぼしていることがあるのです。生活全般の情報を収集し、問題点との関連をみていくことが大切です。
確認した内容をもとに、どこをどのように改善できるか、患者さんと一緒に考えるようにします。例えば、外食が多いなら、丼ではなく食品数の多い定食にしたり、不足しがちな野菜、海草、きのこ類などを家庭で多く取るようにするなど、できる方法を探っていきます。
続いて、患者さんが食べ過ぎている自覚がない原因について説明します。
カテゴリの新着記事

糖尿病による血糖コントロール不良で低血糖リスクのある患者さんに関する看護計画
糖尿病による血糖コントロール不良で低血糖リスクのある患者さんに関する看護計画 糖尿病は慢性的な血糖値の上昇とそれに伴う異常が生じる疾患で、インスリン分泌低下によって生じる1型と、インスリン抵抗性による2型があります。インスリン依存性とインスリン非依存性に分類でき、いずれも
-
-
- インスリン自己注射を行う患者さんへの看護計画|血糖コントロールが必要な患者さん
-
-
-
- 食事指導に関する看護計画|糖尿病の患者さんへの食事指導
-
-
-
- 血糖コントロールに関する看護計画|糖尿病の患者さん
-
-
-
- 中心静脈栄養(TPN)の看護|目的、適応・禁忌、手順・介助、合併症とケア
-
アクセスランキング
心電図でみる心室期外収縮(PVC・VPC)の波形・特徴と
心室期外収縮(PVC・VPC)の心電図の特徴と主な症状・治療などについて解説します。 この記事では、解説の際PVCで統一いたします。 【関連記事】 * 心電図で使う略語・用語...
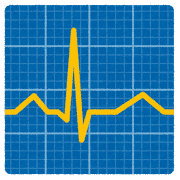
【血液ガス】血液ガス分析とは?基準値や読み方について
血液ガス分析とは?血液ガスの主な基準値 血液ガス分析とは、血中に溶けている気体(酸素や二酸化炭素など)の量を調べる検査です。主に、PaO2、SaO2、PaCO2、HCO3-、pH, ...

人工呼吸器の看護|設定・モード・アラーム対応まとめ
みんなが苦手な人工呼吸器 多くの人が苦手という人工呼吸器。苦手といっても、仕組みがよくわからない人もいれば、換気モードがわからないという人などさまざまではないでしょうか。ここでは、人工呼...
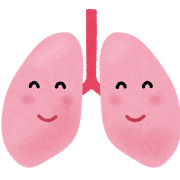
吸引(口腔・鼻腔)の看護|気管吸引の目的、手順・方法、コ
*2022年12月8日改訂 *2022年6月7日改訂 *2020年3月23日改訂 *2017年8月15日改訂 *2016年11月18日改訂 ▼関連記事 気管切開とは? 気管切開...

SIRS(全身性炎症反応症候群)とは?基準は?
*この記事は2016年7月4日に更新しました。 SIRS(全身性炎症反応症候群)について解説します。 SIRS(全身性炎症反応症候群)とは? SIRS(全身性炎症反応...

採血|コツ、手順・方法、採血後の注意点(内出血、しびれ等
採血とは 採血には、シリンジで血液を採取した後に分注する方法と、針を刺した状態で真空採血管を使用する方法の2種類があります。 採血の準備と手順(シリンジ・真空採血管) 採血時に準備...

心電図の基礎知識、基準値(正常値)・異常値、主な異常波形
*2016年9月1日改訂 *2016年12月19日改訂 *2020年4月24日改訂 *2023年7月11日改訂 心電図の基礎知識 心電図とは 心臓には、自ら電気信...

サチュレーション(SpO2)とは? 基準値・意味は?低下
*2019年3月11日改訂 *2017年7月18日改訂 *2021年8月9日改訂 発熱、喘息、肺炎……etc.多くの患者さんが装着しているパルスオキシメータ。 その測定値である...

第2回 全身麻酔の看護|使用する薬剤の種類、方法、副作用
【関連記事】 *硬膜外麻酔(エピ)の穿刺部位と手順【マンガでわかる看護技術】 *術後痛のアセスメントとは|術後急性期の痛みの特徴とケア *第3回 局所浸潤麻酔|使用する薬剤の種類、実施方...

第2回 小児のバイタルサイン測定|意義・目的、測定方法、
バイタルサイン測定の意義 小児は成人と比べて生理機能が未熟で、外界からの刺激を受けやすく、バイタルサインは変動しやすい状態にあります。また、年齢が低いほど自分の症状や苦痛をうまく表現できません。そ...






